強相関電子系の夢は終わらねぇ!@ジョン・ホプキンス大
【イントロ】
多くの物質では、電子相関の効果は相関のない状態に対する摂動として扱われます。一方で、電子相関が本質的な物質もありそこでは電子相関は摂動として扱えず、電子相関のある状態とない状態を断熱的に接続できない状態が実現しています。
この強相関電子状態については、数十年に及ぶ研究にも関わらず、多くの未解決問題があります。強相関電子系を統一的に記述することは可能なのか、それとも、アンナ・カレーニナ原理に基づき、「相関のない電子系はどれも似ていて、強相関電子系はそれぞれ異なっている」のでしょうか?
そうした強相関電子系の未解決問題を、6人のシニア研究者と46人以上の若手研究者がジョン・ホプキンス大に集まり議論した成果が、
"The Future of the Correlated Electron Problem", arXiv:2010.00584
です。
とはいえ55ページの論文読むの大変です。貴重な休日にコレを読もうと思うのは、仕事のストレスで脳をやられた異常者くらいです。
そこで本記事では、この論文の内容を要約してみました。この記事を読んで興味を持たれた方はもとの論文を読んでみてください。
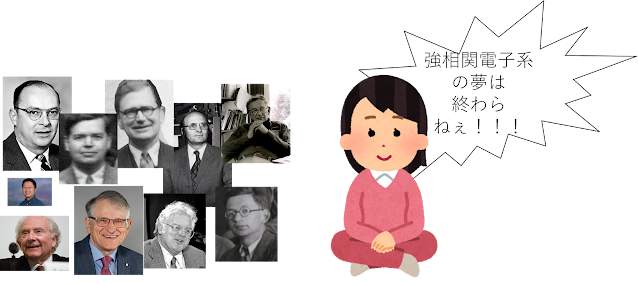 |
| まとめ |
【要約】
「問題」とはなにか
- この論文では、強相関電子系の問題を以下のように定義しています。
- 「強相関電子系問題とは、相互作用が非常に強い、あるいは、そのような性質を持っているために、元の「裸の」粒子に基づく理論では、物質特性を質的にさえ記述できないような問題である」
各種問題(A~Fの6つの課題)
A、強相関電子系の超伝導
- 対象になる問題:
- Migdal-Eliashberg理論やその拡張である電子-フォノン結合をペアリング機構とする理論ではうまく説明できない超伝導体のメカニズムの解明
- 例)銅酸化物、鉄系、重い電子系、有機物、ルテネイト、ニッケル酸化物、カルコゲナイド、捻りグラフェン
- 想定される解:
- 電子フォノン相互作用のBCS理論のような単一の相互作用にではなく、He3のp波超流動のように複数の相互作用によって超伝導が発現している可能性が高い
- ただし、ある特定のメカニズムが非従来型超伝導体に寄与しているかどうか説明できないかもしれないという事実は、定量的な質問に対して答えることができないことを意味しない
- そのような議論の1つは、超伝導の形成においてどのようにエネルギーが節約されるかという点
- 中心的な未解決問題:
- 超伝導の対形成メカニズムはなにか?
- どのようにエネルギーが節約されるか?
- 秩序変数はなにか?
- 異なる系が同じような相図となるのはなぜか?
- 電子構造の次元性の役割はなにか?
- 将来の方向性:
- ペアリングのメカニズムが明らかになるならば、新しいポンププローブ方式の測定によって、異なる自由度やサブシステム間の結合を直接研究すること
- ペアリングの糊の同定に失敗した場合でも、ある種の分光学的手法により、超伝導凝縮エネルギーがω、q、k空間のどこから来るのかを直接特定すること
- もし電子相関が超伝導に重要であれば、層状超伝導体における誘電体環境の違いによってクーロン相互作用がどのように遮蔽されているかを理解することで、ペアリングの性質に対する洞察を得ること
- 非従来型超伝導体の秩序変数の対称性を位相感度の高い測定によって実験的に同定すること
- 相関をもつ超伝導体の相図に共通する特徴を明らかにすること
- 異なる相がメゾスコピックおよびミクロのスケールでどのように相互作用し、競合しているかを理解すること
- 集束イオンビーム(FIB)などのナノ加工技術の進歩により、寸法効果や輸送異方性を調べるための高度に制御されたデバイス形状を実現すること
- 広範囲にチューニングできるパラメータをもつモデルシステムを特定すること
B、量子スピン液体
- 分野の課題
- 多くの量子スピン液体候補物質が調べられてきたが、どれも決定的に量子スピン液体と判明した物質がないこと
- 量子スピン液体の定義として、「ゼロ温度で長距離磁気秩序がないもの」という定義があるが、不十分。文字通りであれば量子常磁性体と呼ぶべき。
- 最近の提案としては、「長距離エンタングルメントの存在」「分数励起の存在」が量子スピン液体の定義として挙げられている
- ただし、中性子散乱実験からいくつかの結果が得られているが、上記2項目について決定的な実験的兆候が得られていない
- 進展の方向性
- 新しい中性子分光法の開発
- 熱輸送測定法の開発
- 不純物周りのスピン密度の可視化
- エンタングル中性子ビーム法の開発
- スピントロニクス用デバイスの製造
- スピン雑音の測定
- 非平衡状態からの緩和の観測
- 多次元コヒーレントテラヘルツ分光
C、異常金属
- 現象の定義
- 金属は、抵抗率がMott-Ioffe-Regel(MIR)限界を破っていなくても、破れている領域と滑らかにつながっているように見える場合は「Bad metal」と呼ぶのが一般的
- さらに、これらの材料の多くは、抵抗率が温度に対して線形であり、MIR値を滑らかに通過する「Strange metal」の挙動を示す
- 量子臨界点(QCP)が近いことを示唆するような、温度による観測値のスケーリングがしばしば見られる
- Strange metalは輸送中にその最も顕著な特徴を示すが、一粒子スペクトルの特徴との関連はあまり明確ではない
- 重要な点は、Strange metalの輸送特性と一粒子スペクトルは、明らかに等価ではない
- 重要な疑問と展望
- 新しい多粒子プローブの開発により、非線形性を定量化することでウィックの定理の破綻を解明したり、より一般的な相互作用効果の詳細を明らかにすること
- MIR限界付近の高温で、キャリア密度、抵抗率、その他の物理パラメータ(帯磁率、比熱、熱拡散率、一粒子分光関数)を協調的に測定することにより、散逸機構の本質を明らかにすること
- 異なるプローブで見られる銅酸化物のStrange metal現象の一貫した記述の追求に加えて、その記述を一般化し、他の物質系での普遍性を追求する努力は、新しい展望をもたらす
- 今後数年間の課題は、散乱率τtrを明確に定義し、もし存在するならば、そのような境界を導き出すこと。一方、係数αを制約するために、できるだけバイアスの少ない輸送時間スケールを抽出する実験を行うこと。
- ここで散乱率の上限がτtr ≥ αh/kBTとなることが報告されており、プランク限界であると言われている
- 最近、1つのレーザーで局所的な温度勾配を作り、2つ目のレーザーの反射率で熱拡散率を測定する新しい光学的手法により、τtrのさらなる実験的研究の可能性が開かれた
- 相関電子系量子物質における非フェルミ液体の振る舞いとStrange metalにおける局所的な電子と遍歴的な電子の性質の間の関係を明らかにすること
- Strange metalの問題に理論的に取り組むには、微視的アプローチと現象論的アプローチの両方が重要
D、量子臨界性
- 分野の現状
- 従来は、Landau-Ginzburg-Wilson (LGW) パラダイムの中で、量子臨界性は記述されていた。また、対称性の破れた状態への連続遷移における秩序変数のダイナミクスを捉えるために繰り込み群法が拡張されて利用されてきた
- LGWの枠組みは、2つの異なる秩序相の間の連続的な転移を扱うことができず、対称性の破れによって特徴づけられない相や相転移を記述することができない
- LGWの限界は、モデル系や物質例で実証されている
- 直線的な温度抵抗のようなStrange metalの振る舞いがQCPの近くで観察されている。このような振る舞いは「相」と関連しているようだが、疑問は、このような非フェルミ液体的振る舞いが、臨界モードに結合したフェルミ面を持つ枠組みで説明できるのかどうかということ
- 3次元の反強磁性転移は平均場的であることが多いが、反強磁性揺らぎと節点の電子が強く結合したノーダル金属では、QCPにおいてエキゾチックなスケーリングが予言されている
- 重い電子系金属は、臨界に関する最も単純な考察を回避しているように見える系が数多く存在する
- そのため、このような物理を理解するためには、新しい理論的枠組みが必要になるかもしれない。一つの理論的なシナリオは、重い電子系の臨界点が、反強磁性秩序の発現ではなく、「近藤ブレイクダウン」に関連するというもの
- 局所量子臨界の枠組みでは、局所モーメントは伝導電子だけでなく他のモーメントの揺らぎとも結合しているため、近藤効果は破壊されてしまう
- 重い電子系と銅酸化物の臨界点には、関連した物理が隠されていると予想される。興味深いのは、重い電子系と銅酸化物がともにMott極限にあることで、大きなハバードUがヒルベルト空間に対して二重占有を禁じる制約を与えている
- 2次元超伝導体-絶縁体転移は、量子相転移の重要なモデル系と考えられている
- QCP近傍に二次的な秩序が発生する可能性で、その最も顕著な例が超伝導である
- 新しいフレームワーク
- 過去20年間に、LGWの枠組みを超えた新しい臨界理論として開発されたのが、「脱閉じ込め量子臨界性」の概念である
- 重い電子系や銅酸化物における金属-金属転移と関連づけるためには、既存の脱閉じ込めQCPをより高度に一般化する必要
- しかし、理論的に探求されている脱閉じ込め量子臨界の実現は、ほとんどが絶縁体-絶縁体転移に限定されている
- QCPと乱れの効果に関する実験と理論の理解をより深めるために、以下のワークフローを提案する
- 乱れの種類とレベルを特定する
- 第一原理計算による有効不純物ポテンシャルの推定
- 前ステップの実験で得られた特定の有効不純物ポテンシャルを入力とするモデル計算(数値および解析)を行い、異なるタイプの無秩序を含むまたは含まない類似の計算と比較
- 量子臨界のモデル物質として、標準理論とその拡張の両方が検証できるような、より良いモデル物質系を同定する。
- 同時に、対称性、トポロジー、動的相関、スケーリング則などを解決する、より高度で包括的な測定技術が必要とされている
E、強相関トポロジカル物質
- 進展と課題
- この10年間、バンド理論と代数的トポロジーの交差点において、非常に活発な理論的・実験的活動が行われてきた
- 現在、トポロジカル金属に相関を導入する研究が進められている。その結果得られる物質の相関相は必ずしもトポロジカルではないが、豊かな物理を持つことが多い
- 相互作用するトポロジカル物質の厳密な分類は未完成である
- 相関絶縁体(TBGなど)の理論的理解の進展により、一粒子バンドトポロジーと多体相関の間に洞察に満ちた関係があることが示されている
- この分野の現在のボトルネックは、強く相互作用するトポロジカル物質の物質候補が非常に少ないこと
- 材料候補の不足は、トポロジカル超伝導体において特に深刻。近接効果駆動型2次元超伝導体という当初の提案には、今のところ説得力のある証拠はほとんどない
- さらに、この分野では、強相関トポロジカル絶縁体の決定的な兆候を見つけることも課題
F、既存物質の見直し
現代の研究者にとっては、新しい実験方法を校正するための実験台として、古くてよく研究されている材料を調べることは有益なこと
- 金属
- 磁性や超伝導がない場合でも、多くの金属で従来とは異なる輸送特性を示すことがあり、これが相関電子問題へのヒントになると考えられる
- 興味深いのは、液体金属である。液体金属は、結晶秩序がなく、したがって従来の電子バンドやフォノンバンドという概念もない
- 半金属
- 半金属とは、電子と正孔の両帯域がフェルミ準位と一致、または近接している物質のこと
- グラファイト、ビスマスなど
- 古い半導体の価値を見直すきっかけとなったのが、近藤絶縁体SmB6
- 重い電子バンド(磁気モーメントが「ほぼ局在」している)と軽い電子バンドが混成し、フェルミレベルでギャップが生じる物質
- 最近、SmB6で量子振動が観測され、電荷中性のフェルミ面を示唆したことから注目を集めたが議論の余地がある
- 半導体と絶縁体
- 実用面では、半導体物理学は20世紀後半を通じて革新的な新技術を生み出し、固体物理学の圧倒的なサクセスストーリー
- 古い半導体が新しい物理の源泉として機能し続けている典型的な例として、SrTiO3がある
- 世界で最もよく研究されている半導体であるシリコンでさえ、強相関電子物理学の未解決の問題を解決するための有益なプラットフォーム
- ある種の半導体(例:Cu2Se)は、構造相転移の近傍で異常な電子物性を示す
- 超伝導
- 多くの「古い」超伝導体の対形成メカニズムの詳細は、まだ十分に理解されていない
- ドープされた半導体の中には、銅酸化物に似た「超伝導ドーム」を形成するものが多数存在
- ビスマスの超伝導特性も同様に魅力的
- 「high-Tc」的超伝導ドームな現象は、元素磁性金属でもみられる
今後の取組の方向(A~Gの7つの方向性)
A、物質合成と発見
- 既知の物質や新しく作られた物質が、現在の宇宙の理解や理論では明らかに説明できない現象や振る舞いを示すとき、物質的発見が起こったと言える
- 材料系の科学者は、少なくとも4つの面で極めて重要な存在。
- 新しい材料や興味深い材料の発見
- 既存材料の品質向上
- 材料特性を変えるためのドーピングなどの利用
- ヘテロ構造および新材料構成の開発
- 特に、新規な高分子構造を持つ材料の設計は、有望な方向性
- 相関電子問題の将来を考える上で、材料合成の重要なテーマは、原子レベルとメゾおよびマクロレベルの両方で、無秩序と欠陥の役割を理解すること
- 今後の方向性としては、新規相を安定化させる構造モチーフを予測する理論、材料合成、特性評価との間のフィードバックループを重視する必要
B、数値計算手法
- 数値(計算)物理学には、次の3つの役割がある
- 微視的モデルや多体系モデルと複雑な実験系をつなぐなど、解析理論と実験の橋渡し的な役割
- 新しいタイプの(数値)実験が容易になる。
- 数値シミュレーションは、物理的な実験よりも安価で、高速に、そして簡単に制御することが可能になる
- 解析的な記述が不可能な複雑なシステムを記述するための理論的なツール
- 最新の計算機技術により、解析理論の枠組みでは解けないことが多い物理量の近似を、適切に制御して利用することができる
- 数値計算方法はブラックボックスとして扱われるべきではない。
- その限界は明確に述べられ、研究結果との理論的なつながりを求める実験家を含む実務家とユーザーの両方が理解する必要があります。
- 相関電子問題に対する数値計算手法の限界は、フェルミオン符号問題である。
- この問題によって、厳密なモンテカルロ法のいくつかは、相互作用するフェルミオンやフラストレート・スピン系の一般的なモデルへの適用が制限されている
- 強相関電子系の基本的な物理原理を理解し、理論と実験を関連付けるために不可欠な、計算が困難な興味ある量がある
- 人工知能、機械学習、量子コンピュータ、量子シミュレーションなどの技術が急速に発展し、数値計算技術が強相関電子問題に取り組む上で重要な役割を果たすと予想される
C、解析計算手法
- 新しいアプローチ
- 相関電子問題を解決した顕著な例として、分数量子ホール効果(FQHE)がある。ここでは、系の特性を説明する基底状態の波動関数が明示的に構築された
- スピン液体のKitaevモデルの例は、望ましい基底状態を持つToyモデルを提案することが、理論理解と将来の実験ガイドの両方で途方もない進歩につながることを示す
- 相関電子問題を進展させるもう一つの戦略は、量子力学的記述の一般的な対称性や性質を利用して、相関の強さに関係なく有効な厳密な記述を導き出すこと
- ある種の観測量に対する境界は、かなり一般的な考察から解析的に導き出すことができるため、相関系にも適用することが可能
- 「類推理論」とは、ある物理分野の類似性を他の物理系で調べ、対応する問題への新しい洞察を得ること
- 非平衡状態への適用
- 非常に複雑な相関電子系における非平衡現象を調べるには、解析ツールボックスをさらに発展させる必要がある。
- 特に重要な方向性は、周期駆動多体系である。
- これまで、2つの理由で進歩は限られていた。
- 第一に、一般的な相互作用系は「閉じない」代数を持っており、これが複雑な有効ハミルトニアンを導くため、進展を妨げてきたため
- 第二に、相互作用のある場合、高周波数の展開は、収束的な展開ではなく、せいぜい漸近的な展開と考えられるため
- 近年、時間的に独立なハミルトニアンの相互作用に対する同様のアプローチ、いわゆるWegnerフローアプローチが開発されている
D、新しい分光手法
- 課題
- 相関電子問題の重要な課題は、多くの場合、電子の運動量kと電子間の運動量移動qが、長さ、エネルギー、時間の広い範囲にわたってシステムを記述するための良い変数でなくなってしまうこと
- 最新の分光手法
- 電荷、スピン、軌道、格子自由度の一粒子スペクトルや二粒子(もしくはそれよりも高次の)相関関数を測定する手法、そしてそれらの組み合わせが必要
- ARPES、STM、NMR、RIXSなどMBEによるサンプル作製が組み合わされている
- 最近、s軌道非共鳴非弾性X線散乱が開発され軌道占有状態の可視化が可能になった
- 将来の開発の方向性
- ほとんどの分光学的手法は、線形応答の極限における準粒子励起のスペクトル関数や2粒子相関関数に着目している。
- 相関電子系は、これらのスペクトル関数や相関関数に直接現れない、対称性が守られた相や対称性が破れた相を持つ場合がある
- 従来の線形応答技術の枠を超えて、高次の感受率を探索する分光法が必要
- 多くの物質では隠れた秩序が存在し、熱容量などの熱力学量では相転移の明確な兆候を示し、従来の分光学的手法ではギャップ形成の兆候を示すが、従対称性の破れの性質についてほとんど情報が得られない
- URu2Si2の隠れた秩序や銅酸化物の擬ギャップ相など
- 「従来の」分光学ではアクセスできない応答関数を抽出するために、粒子(絡み合った中性子、光子、電子など)のペアを使用したり測定したりするツールも、将来有望な方向性
- オージェ光電子同時計測分光法(APECS)
- 量子系の本質的な性質である長距離のもつれを調べることは、非常に強力であるが、それ以上に大きな困難を伴う
E、局所測定手法
- 課題
- 多くの強相関系では、清浄な系であっても局所的に競合したり共存したりする多数のほぼ縮退した相が見られる
- 個々の相を単独で調べるだけでなく、それらの相互作用がどのように巨視的な挙動に寄与しているかを理解するためには、空間分解測定が不可欠
- STMやTEM
- 新しい測定手法
- 近年、新しい顕微鏡法も開発され、その初期段階にもかかわらず、有望な感度や空間分解能を示すようになった
- 走査型SQUID
- ダイヤモンドNV中心顕微鏡
- ナノX線回折
- コヒーレントX線イメージング
- 今後の課題として重要視される可能性のあるいくつかの分野
- 相関のある物質特有のニーズに対応した試料環境や操作プロトコルを開発
- 理論モデリングにより、実験観測と電子応答や相関関数の理論計算を結びつけるために不可欠
- 同じ空間、同じ条件下で、相関のある物質のマルチモーダルな探索を行うコンソーシアム、あるいは共同研究の仕組みを構築
- 顕微鏡測定と機械学習の組み合わせ
F、非平衡状態の分光手法
- 現状
- 非平衡分光法は、異なる自由度を分離する新しい道を提供し、集団励起、準安定・過渡状態、揺らぎを研究することが可能
- 時間分解反射率測定や時間分解光電子分光など、強相関物質の時間分解非平衡研究の多くは、約1.5eVのエネルギーでの光励起を多用
- HHGベースの技術は時間領域で次の2つの重要な情報を提供する
- XUV/X線吸収分光法により局所結合、磁化、格子構造の元素固有の進化
- 光電子のホログラフィック検出による位相敏感性
- 今後の展望
- 円偏光により時間反転対称性を破り、フラストレートなモット絶縁体をキラルなスピン液体へと駆動する
- 近藤崩壊QCP近傍における、電子寿命はマルチスケールの温度スケーリング則に従った発散を時間分解光反射率および光電子分光法で測定する
- テラヘルツ励起と光電子分光や走査型トンネル分光などの他の分光プローブを組み合わせることで、集団モードの運動量依存性や空間依存性を明らかにする
- 相競合を駆動してオーダーパラメーターを研究する
- 時間分解STM、時間分解走査型SQUID、時間分解中性子回折、時間分解RIXSは、非平衡分光の具体的な将来の方向性
G、極限環境の測定手法
極端な環境条件は、新しい相関状態が誘起したり、既存の相に関与する相関のエネルギースケールを探るために利用される
- 超低温
- 例えば、分数量子ホール効果は5mKで発見された
- 高電場・高磁場
- 約1V/Åの強電場は、強相関系における相転移を調整するためのもう一つの切り札
- 2012年にロスアラモス国立研究所でパルス磁場で100Tに到達し(現在、他の高磁場研究所でも利用可能)、非破壊磁場の最高値が実現
- 大きな上部臨界磁場を持つ一部の銅酸化物の正常状態を研究するために、さらに高い磁場に長時間アクセスするための新しい技術開発が必要
- 残念ながら、従来のARPES実験では磁場をかけることができないが、大電流(10^6A/cm2 )での光電子分光実験は行われている
- 高圧力・高歪み
- 最近では、90GPaという高い圧力でNMR実験を組み合わせることに成功
- 高圧力とARPESのような高表面感度の技術を組み合わせることは、明白な理由により、全く達成されていない
- 単軸ひずみは相関系の電子・磁気特性を研究するために最もよく使われる手法の1つ
- 例えば、STM、SEM、ARPESなどの実験用プローブは、単結晶や薄膜に対して一軸性歪みを利用可能
- 今後の課題と展望
- 複数の極限環境を組み合わせたプローブは、実験の難易度が高い
- 多くの高度な散乱、分光、顕微鏡測定の実験的な複雑さは、極端なサンプル条件へのアクセスにも大きな挑戦
まとめ
- この原稿では、「相関電子問題の将来」について議論した結果を整理することを試みた
- 進歩にはサイクルがあり、今後は困難な古い問題に新しいアイデアで立ち向かっていくことに意味がある
- 一方で、再現性の問題、過剰な分析・解釈、専門用語の多用、インパクトのある論文を作らなければならないというプレッシャー、「新しさ」の追求のために系統だった研究が行われないといった問題は、間違いなく相関電子コミュニティだけの問題ではない
- 実際、最近、実験データの再現性に関するいくつかの注目すべき事例が報告されている
- Sr2RuO4超伝導におけるトリプレットペアリング
- Ca2RuO4における巨大電流誘起反磁性
- 量子異常ホール超伝導デバイスにおけるカイラルマヨラナフェルミオン






コメント
コメントを投稿