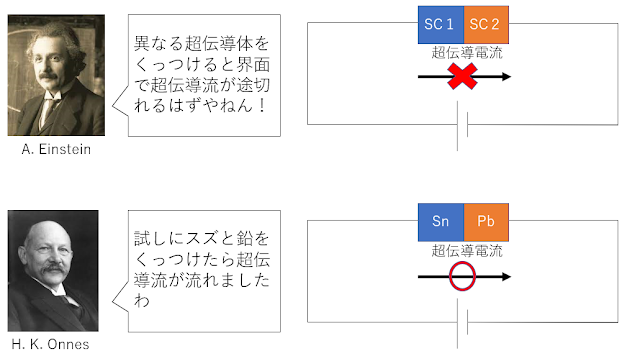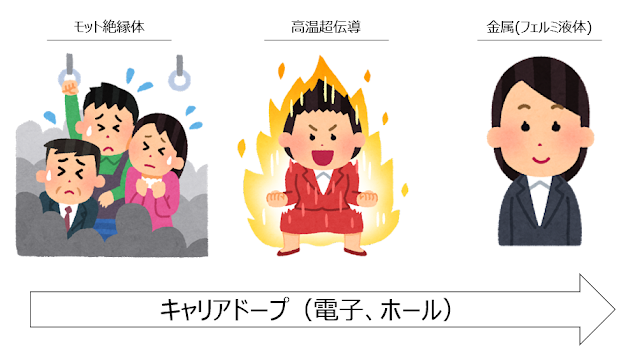人類みんな光物性研究者!~高温超伝導体の電荷応答を読んで~

【イントロ】 世の中にはいろいろな研究があります。 その中で、 物性研究 とは、物質の持つ物理的な性質、例えば、機械的性質(力学的性質)、熱的性質、電気的性質、磁気的性質(磁性)、光学的性質(光物性)を研究することを指します。 この中で、もっとも研究者が多いのはどの分野でしょうか? 物質の研究をするとき、最初にすることはなんですか? 電気抵抗率を測る?磁化率を測る?熱伝導率を測る? 違いますね? まず最初に行っている実験は、物質を「見る」、つまり物質に入射した光が物質表面で反射する電荷応答を観測することです。 つまり、人類は皆、光物性の研究者なのです!!! そこで、本記事では物質の中でも電子同士の相関が重要となる高温超伝導体の電荷応答について解説された最新の教科書、 田島節子 著 高温超伝導体の電荷応答 強い電子相互作用がもたらすエキゾチックな物性 の感想について記したいと思います。 J( 'ー`)し ※特に意味はないです 【概略】 まずこの本は目的は以下のようにまえがきに記されています。 エキゾチックな超伝導体の物性について、電荷応答の観点から解説することを目的としている。さらに、これらの例を学ぶことで、より一般的な他の類似現象についての理解も深めてもらうことが、究極の目的である。 つまり、この本ではエキゾチックな超伝導体、つまり銅酸化物超伝導体や鉄系化合物超伝導体の電荷応答を題材に、光物性の基礎知識および最先端の研究テーマを学ぶことができるということです。 最高ですね。一粒で二度美味しい。 お値段4200円+税込みですが、実質2100円ともいえるお得さです。 また、本書対象者は、以下のように記されています。 大学の学部4年生から大学院修士課程の学生の知識レベルを想定して書かれている。電磁気学、量子力学、統計力学、そして簡単な物性物理の知識があることが望ましい。 エキゾチックな超伝導体や強相関電子系の光物性に興味をもつ学生、研究者は、自宅・研究室に1冊は置いておきたい教科書です。 実質半額であることを考えると、自宅と研究室用に2冊買ってもいいかもですね。 以下では、この本を読んで良いと思ったところ、コレがあればもっと良かった思ったところを記したいと思います。個人の感想なので許してください。 【良かったところ】 1,赤外分光法やラマン分光法の基本...